入管事件に関するご相談・ご依頼について
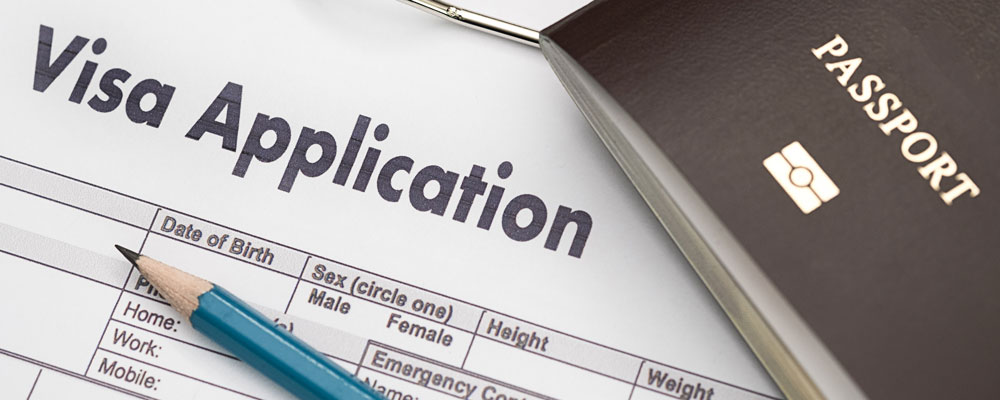
- 日本で就労ビザを取得したい外国人の方
- 家族を外国から呼び寄せたい外国人の方(在留資格認定証明書交付申請)
- 日本で事業を始めたい方
- オーバーステイで逮捕されたが日本人と結婚したいなどの理由で日本に残りたい方(在留特別許可の取得)
- 退去強制令書の発付を受けてしまったが裁判をしたい方(退去強制令書発付処分等取消請求訴訟)
- 出入国在留管理局における収容から収容者を解放したい方(旧:仮放免・新:監理措置)
などの案件についての相談・ご依頼を承っています。
こんなことでお困りではありませんか?
- 私は留学生として来日して、日本企業に就職しました。どのビザに変更すべきですか?
- 私は日本でITエンジニアとして働いていますが、母国で暮らす妻と子を呼び寄せて日本で暮らしたいです。呼び寄せは可能ですか?
- 私は、日本で会社を設立して貿易ビジネスを行いたいのですが、どんな条件を満たせばビザがもらえますか?
- 私はビザの期限を過ぎて日本に滞在していますが、結婚相手と一緒に日本で暮らしたいです。ビザをもらうことはできますか?
- 私はオーバーステイで捕まり、現在出入国在留管理局に収容されていますが、外に出ることは可能でしょうか?
- 私は退去強制令書の発付を受けてしまいました。裁判をできると聞きましたが、どうしたらよいでしょうか?
- ビザをもらうために裁判を起こしましたが、負けてしまいました。その後、日本人と結婚しましたが、またビザをもらえる可能性は残されていますか?
このようなビザに関する問題がございましたら、名古屋国際法律事務所までご相談をください。
取り扱い内容詳細
ビザの変更
留学ビザなどから就労ビザへの変更は、条件を満たせば可能です。
日本で働くためには一定のビザ(在留資格)が必要です。留学のビザでも、資格外活動許可を取れば、週に28時間まで働くことができます。しかし、留学のビザのままフルタイムで働くことはできません。そこで、フルタイムで働くことができるビザに変更する必要があります。
もっとも、どんな職種であってもビザがもらえるわけではありません。一般的に、単純労働に従事しているだけでは、就労のためのビザはもらえません。例えば、ITエンジニアとして働くのであれば、技術・人文知識・国際業務のビザに変更することが考えられます。レストランのコックとして働くのであれば、技能のビザが考えられます。
また、職種の要件とともに、職務経験、学歴、給与額などの要件が必要である場合があります。例えば国際業務のビザであれば一般的に3年以上の関連職務経験が必要ですが、通訳などの業務に従事する場合には不要です。
名古屋国際法律事務所では、ビザの変更申請のご依頼を受けた場合には、依頼者の方がどのビザの条件に当てはまるかを検討し、その申請に必要な書類をご案内し、出入国在留管理局に対して代理で申請を行います。名古屋国際法律事務所に所属する弁護士は、全員、出入国在留管理局に対して取次業務を行う旨の届け出を行っています。また、依頼者の方の事情をお聴きした上で、出入国在留管理局宛の上申書を作成し、申請時に提出します。

よくある質問
|
Q. |
ビザの期限がそろそろ切れてしまうのですが、ビザの変更は間に合いますか? |
|---|---|
|
A. |
現在のビザの期限内に申請をすれば、原則として、最大で2か月間現在のビザの期限が延長されます。もっとも、申請のためには、様々な書類を準備する必要があり、一定の準備期間が必要ですので、できるだけ余裕をもってご相談ください。 |
|
Q. |
一度自分でビザの変更を申請しましたが、入管から不許可と言われました。もう一度申請することはできますか? |
|---|---|
|
A. |
できます。入管に相談に行けば、詳しい不許可理由を教えてくれます。前回ビザの変更が不許可とされた理由によっては、その問題をクリアした上で再度申請をすることで、許可を得ることが可能です。 |
|
Q. |
申請が不許可とされたことに不服がある場合、裁判で争うことはできますか? |
|---|---|
|
A. |
できます。不許可とする通知を受けた日から6か月以内に裁判を起こすことができます。名古屋国際法律事務所では、弁護士が申請から裁判までを行うため、申請時の事情を良く把握している者が裁判を担当することができます。 |
|
Q. |
申請から結果が出るまでどのくらいかかりますか? |
|---|---|
|
A. |
在留資格変更許可申請の一般的な処理期間は、1か月~2か月程度です。もっとも、個別のケースでそれよりも長期間を要する場合があります。 |
親族等の呼び寄せ
あなたが一定の在留資格で日本に滞在している場合、条件を満たせば、親族等の呼び寄せが可能です。
親族等を呼び寄せて長期間日本で暮らすには、通常、在留資格認定証明書の交付を申請します。在留資格認定証明書は、呼び寄せられる方が、一定の在留資格に該当し、日本に上陸するための基準を満たしているかどうかを、あらかじめ審査するものです。もっとも、来日するためには、在留資格認定証明書の交付を受けた後、改めて現地の領事館での査証(ビザ)申請をすることが必要です。
例えば、中古自動車を輸出する会社で働いている方であれば技術・人文知識・国際業務の在留資格を有しているものと考えられ、その妻や子は家族滞在のビザでの来日が考えられます。もっとも、家族を養うことが可能な一定の収入を得ている必要があります。
ただし、短期滞在など一部の在留資格での呼び寄せについては、在留資格認定証明書交付申請をすることができません。
名古屋国際法律事務所では、親族等の呼び寄せのご依頼を受けた場合には、呼び寄せたい方がどのビザの条件に当てはまるかを検討し、その申請に必要な書類をご案内し、出入国在留管理局に対して代理で申請を行います。所属する弁護士は、全員、出入国在留管理局に対して取次業務を行う旨の届け出を行っています。また、依頼者の方の事情をお聴きした上で、出入国在留管理局宛の上申書を作成し、申請時に提出します。

よくある質問
|
Q. |
外国人と結婚しましたが、その人は過去に日本でオーバーステイをしたことがあるようですが、呼び寄せは可能ですか? |
|---|---|
|
A. |
オーバーステイなどの理由で日本を離れた方は、一定の期間(例えば5年間など)は来日が原則としてできません。もっとも、一定の人道的配慮が必要な場合には、上陸拒否期間中であっても、特別に上陸が許可される場合があります(上陸特別許可)。名古屋国際法律事務所では、上陸拒否期間中であっても、来日が必要な事情を説明し、上陸特別許可の取得を目指します。 |
|
Q. |
在留資格認定証明書の交付申請が不許可とされたことに不服があるので、裁判で争うことはできますか? |
|---|---|
|
A. |
できます。不許可とする通知を受けた日から6か月以内に裁判を起こすことができます。但し、裁判で勝てる可能性は必ずしも高くありません。なお、在留資格認定証明書交付申請は、何度も行うことが出来ますので、弁護士に相談をして、不許可理由を入管に確認して、再度の申請を行うことも検討に値します。 |
|
Q. |
申請から結果が出るまでどのくらいかかりますか? |
|---|---|
|
A. |
在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は、1か月~3か月とされています。もっとも、個別のケースでそれよりも長期間を要する場合があります。 |
|
Q. |
私の父親が老齢で一人暮らしのため、日本に呼び寄せて面倒をみたいです。呼び寄せは可能ですか? |
|---|---|
|
A. |
老親扶養のための特定活動のビザを取得できる可能性はありますが、このビザは告示であらかじめ定められているものではないので、在留資格認定証明書の交付申請はできません。親御さんの呼び寄せの実現のためには、まずは短期滞在で日本に入国して、その後、在留資格の変更手続をとる必要があります。但し、最近、老親扶養の特定活動の在留資格の付与は、非常に厳しくなってきています。 |
経営管理ビザの取得
日本で新規に会社を設立し、経営管理ビザを取得して来日するためには、原則として、まずは株式会社または合同会社などを設立して代表取締役等になることが必要です。経営管理ビザは、条件が緩すぎるとの批判を受け、2025年10月16日に上陸基準省令等が改正され、取得要件が厳格化されました。主な要件は以下の通りです。
- 資本金:3000万円以上
- 経歴・学歴: 経営者としての経験3年以上または経営管理等に関する修士号または博士号を取得していること
- 雇用義務:1人以上の常勤職員の雇用義務(日本人又は身分系の在留資格で在留している人に限ります。就労系在留資格の方ではだめです。)
- 日本語能力:申請者または常勤職員が日本語能力試験N2相当以上の日本語能力を有すること
- 事業計画の専門家による確認:申請時の事業計画の中小企業診断士、公認会計士、税理士による確認が必要
- 事務所要件:原則として自宅兼事務所では許可されないこととなりました
名古屋国際法律事務所では、会社設立や経営管理ビザの取得のご依頼を受けた場合には、ビザの取得要件や必要書類をしっかりとご説明させていただき、司法書士や税理士とも連携しながら作業を進めて行きます。必要な場合には、事業計画書作成もサポートさせていただきます。申請に必要な条件が整ったら、出入国在留管理局に対して代理で申請を行います。所属する弁護士は、全員、出入国在留管理局に対して取次業務を行う旨の届け出を行っています。

よくある質問
|
Q. |
私は外国に居住しており、資本金を振り込む口座が日本にありませんが、どうしたらよいですか? |
|---|---|
|
A. |
資本金の振込先口座は、原則として、発起人または設立時取締役の口座でなければなりません。このため、従前は、日本国内に口座を有する人に、少しだけ株式を保有してもらい、その方の口座を利用するということが行われていました。しかしながら、現在は、発起人及び設立時取締役の全員が日本国内に住所を有しない場合には、例外的に、委任状を発行することにより、第三者の口座を利用することが可能となりました。名古屋国際法律事務所では、資本金振込先口座の提供も行っています。 |
|
Q. |
株式会社と合同会社はどう違いますか |
|---|---|
|
A. |
様々な違いがありますが、最も大きな違いは、株式会社では、出資者(株主)と取締役などの役員が別の人でもよいですが、合同会社では、出資者(社員)と業務執行社員が同じ人でなければなりません。あなたが一人で会社を立ち上げるのであれば、出資者も役員もあなた一人ですので、どちらでもあまり変わりはありません。2人以上が出資者となって会社を立ち上げる場合には、出資者の一部だけが役員となって会社を運営する場合には、株式会社形態とする必要があります。なお、会社の設立費用は、合同会社の場合、株式会社の半額程度です。 |
|
Q. |
雇用する常勤職員は、技術・人文知識・国際業務のビザを有する人でも大丈夫ですか? |
|---|---|
|
A. |
日本人を雇用しない場合には、いわゆる身分に基づく在留資格を有している常勤職員を一人以上雇用しなければなりません。具体的には、永住者、⽇本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の方が該当します。二人目以降は技術・人文知識・国際業務のビザを有する従業員を雇用することももちろん可能です。 |
|
Q. |
「日本語能力を有する」の要件を満たすためには必ず日本語能力試験を受ける必要がありますか? |
|---|---|
|
A. |
⽇本語能⼒試験(JLPT)N2以上に合格している場合の他、20年以上日本に居住している場合、日本の大学を卒業している場合、日本の義務教育及び高校を卒業している場合には、日本語能力試験を受験していなくても、「日本語能力を有する」とされています。 |
|
Q. |
スタートアップビザを取得してから経営管理ビザを取得することができますか? |
|---|---|
|
A. |
いわゆるスタートアップビザとは、地方公共団体等から「起業準備活動計画確認証明書」の交付をうけた外国人が申請することのできる「特定活動」ビザのことです。これは優秀な外国人起業家を日本に呼び込むための制度で、対象となる事業の分野は、各都道府県などによって異なり、例えば、愛知県では、IT分野や革新的技術を用いた産業分野が支援の対象です。地方公共団体等から「起業準備活動計画」の確認を受けると、6ヶ月または1年の特定活動のビザを申請することができ、このビザは最長2年まで更新をすることができます。当該特定活動のビザで滞在する間に経営管理ビザの要件を満たして、経営管理ビザへ変更することが必要です。 |
|
Q. |
経営管理ビザの取得要件が厳しくなる前から経営管理のビザを持っていますが、これまで通り更新できますか |
|---|---|
|
A. |
2028年10月16日までは、新基準を満たしていなくても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえて許否の判断がなされますので、更新される可能性はあります。2028年10月16日以降は、原則として新基準を満たしていなければ、更新できないとされています。よって、3年間の間に、資本金を3000万円に増額する、常勤職員を1人以上雇用する、日本語のできる常勤職員を採用するなどの対策を取る必要があります。名古屋国際法律事務所では、新基準適合のための支援も行っています。 |
退去強制手続への対応
日本に滞在するビザがなくなった場合でも、退去強制手続の中で在留特別許可申請を行った上で、在留特別許可を取得することが可能な場合があります。
在留特別許可の基準については、入管法50条5項に書かれています。これによれば、「在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなった経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、退去強制の理由となった事実及び人道上の配慮の必要性を考慮するほか、内外の諸情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情を考慮するものとする」とされています。また、出入国在留管理庁の公表する「在留特別許可に係るガイドライン」にもさらに細かい基準が書かれています。
具体的には、日本人や日本に滞在している外国人と結婚している場合などにはプラスの事情として考慮され、日本の法律に違反する行為等を行った場合にはマイナスの事情として考慮されます。
在留資格を更新することなく日本に不法に滞在したり、一定の刑事事件を起こしてしまった場合には、退去強制手続が開始されます。その中で在留特別許可申請を行い、在留が特別に許可されるべき資料を提出し、出入国在留管理局に対して在留特別許可を求めることになります。在留特別許可の申請手続は、弁護士がサポートすることが可能です。また、在留特別許可の拒否を判断するための口頭審理には、弁護士が立ち会うことも可能です。

よくある質問
|
Q. |
どのような場合に、退去強制手続が開始されますか? |
|---|---|
|
A. |
入管法24条各号に該当する場合に、退去強制手続が開始されます。オーバーステイや一定の犯罪で有罪判決を受けた場合などが典型的な例です。 |
|
Q. |
退去強制手続はどのくらいの期間で結果が出ますか? |
|---|---|
|
A. |
それぞれの事案によります。退去強制事由に該当する場合は、入管に収容される可能性があり、その場合には収容開始から30日ないし60日以内に結論が出る場合が多いです。収容がなされない場合には、より長い期間を要する可能性があり、場合によっては、年単位の時間を要することもあります。 |
|
Q. |
口頭審理に配偶者も立ち会うことはできますか? |
|---|---|
|
A. |
入管の許可を得て、親族または知人の一人を立ち会わせることができます。弁護士も立ち会うことが可能ですので、ご不安な場合には、弁護士の立ち合いを求めることをお勧めします。 |
監理措置(新制度)による入管収容施設からの身柄の解放
外国人の方が、入管に収容された場合、従前は、「仮放免許可申請」を行うことにより、身柄の解放を目指しました。しかしながら、2024年6月の法改正により、仮放免は、健康上の理由など限られた場面でしか認められないこととなり、「収容に代わる監理措置」が広く身柄解放のために利用されるべき制度とされました。従前の仮放免の時代と比較すると、許可が出やすい印象はあります。なお、残念ながら、2025年2月現在、収容に代わる監理措置の申請は、被収容者自ら行う必要があり、弁護士による代理は認められていません。
「収容に代わる監理措置」を申請するためには、原則として「監理人」を選任する必要があります。監理人は、仮放免における身元保証人とは異なり、「被監理者の生活状況の把握並びに当該被監理者に対する指導及び監督を行う」とされています。そして、監理人は、被監理人が不法就労している事実を知った場合などには、入管に届け出る義務(通報義務)を負っています。監理人がこの義務に違反した場合には、10万円以下の過料の制裁を受ける可能性があります。被収容者のために「監理人」になろうとする方は、この点十分に注意する必要があります。

よくある質問
|
Q. |
収容に代わる監理措置決定を得るまでには、どのくらい時間がかかりますか? |
|---|---|
|
A. |
2025年現在、申請から2週間から4週間程度というのが実務のようです。 |
|
Q. |
監理措置に付されている間は、仕事をすることはできますか? |
|---|---|
|
A. |
退去強制令書が発付されるまでの間は、就労が許可される場合があります。退去強制令書発付後は、就労は許可されません。 |
|
Q. |
監理措置決定が出て外にいる間に突然帰国させられることがありますか? |
|---|---|
|
A. |
退去強制令書が発付されている場合には、突然帰国させられる可能性があります。弁護士に依頼をして、(出頭に対する)「協力申出書」及び(送還予定時期の)「通知希望申出書」を入管に提出しておくと、送還の概ね2か月前に知らせを受け、強制的に帰国させられないように必要な場合には対策をとることができます。 |
退去強制令書発付処分の取消訴訟
退去強制令書の発付処分を受けてしまった場合でも、裁判を通じて在留特別許可の取得を目指すことができます。
退去強制令書の発付を受けてしまった場合には、通知を受け取った後6か月以内であれば退去強制令書発付処分の取消訴訟を提起することができます。取消訴訟の中では、入管が退去強制手続の中で、考慮すべき有利な事情を十分に考慮しなかったことや重視すべきでない不利な事情を重視しすぎていることなどを主張していきます。裁判所が入管と異なる判断をし、裁判で勝訴する例も数は多くないですが存在します。判断が変わらないまでも、事実上の和解勧告によって、ビザが得られることも相当数あります。
退去強制令書が発付されてしまい、これを取り消すための裁判を起こす場合、依頼者に有利な証拠を収集し、また依頼者の言い分をまとめた陳述書を作成し裁判所に提出します。また、依頼者の声を直接裁判所に届けるために、尋問手続を申請します。裁判での勝訴だけではなく、退去強制令書発付後の事情を主張して、裁判所による事実上の和解勧告によるビザの取得を目指します。

よくある質問
|
Q. |
裁判にはどれくらいの時間がかかりますか? |
|---|---|
|
A. |
個別のケースによりますが、一般的に1年程度の時間を要します。高等裁判所へ控訴した場合、さらに約6か月を要します。 |
|
Q. |
裁判を起こすと、その間は強制帰国させられませんか? |
|---|---|
|
A. |
入管は、法律上は裁判中でも強制帰国させることができますが、裁判中の強制帰国を違法とした判例がありますので、入管は、2025年現在、裁判中に強制帰国はしない扱いをしています。 |
|
Q. |
裁判にはどのような書類を提出したらよいですか? |
|---|---|
|
A. |
個別のケースによって異なりますが、例えば夫婦関係のつながりの強さを証明したい場合であれば、配偶者と一緒に配偶者の方に陳述書を書いていただいたり、お二人で写っている写真などを証拠として用いることが考えられます。 |
|
Q. |
裁判はいつでも起こせるんですか? |
|---|---|
|
A. |
退去強制の決定がなされたことの通知を受けてから、原則として6か月以内に裁判を起こす必要があります(行政事件訴訟法14条1項)。もっとも、その後に事情が大きく変化したなどの場合には、在留特別許可をすることを求めて義務付け訴訟を提起することも考えられます。 |
|
Q. |
裁判には毎回出席する必要がありますか? |
|---|---|
|
A. |
弁護士が代理人として出席しますので、基本的には毎回出席していただく必要はありませんが、もちろん出廷していただくことも自由です。また、裁判所での尋問手続きが開かれる際には必ず出廷が必要となります。その場合は、弁護士と入念に打ち合わせを行っていただくこととなります。 |
退去強制令書発付後の事情変更に基づく在留特別許可の取得とみそぎ帰国(上陸拒否期間の短縮申請)
退去強制令書の発付処分を受け、その取消しが裁判で認められなかった場合でも、その後に大きな事情変更があれば、再審情願による在留特別許可の取得や一旦帰国した上で、上陸拒否期間を短縮して正規のビザでの上陸を目指すなどします。また、再度の裁判を通じて、在留特別許可の取得を目指すこともあります。
退去強制令書が発付された当時は、在留特別許可を認めるべき理由がなかったとしても、その後に日本人と結婚して子をもうけるなどして、日本で生活していかなければならない理由が生じた場合には、入管に職権による在留特別許可をするよう再考を促す(再審情願と呼ばれています)ことが出来ます。また、自費出国許可を申請し、その許可を得た上で上陸拒否期間の短縮申請を行い、1年後の正規ビザでの再入国を目指す方法もあります。場合によっては在留特別許可の義務付けの裁判を通じて在留特別許可の取得を目指す必要があります(義務付け訴訟と呼ばれています)。
在留特別許可の基準については、入管法50条5項に書かれています。これによれば、「在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなった経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、退去強制の理由となった事実及び人道上の配慮の必要性を考慮するほか、内外の諸情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情を考慮するものとする」とされています。また、出入国在留管理庁の公表する「在留特別許可に係るガイドライン」にもさらに細かい基準が書かれています。
再審情願の場合の在留特別許可の基準も、原則として、このガイドラインによります。具体的には、日本人や日本に滞在している外国人と結婚している場合などにはプラスの事情として考慮され、日本の法律に違反する行為等を行った場合にはマイナスの事情として考慮されます。
上陸拒否期間の短縮申請は、「みそぎ帰国」などとも呼ばれています。上陸拒否期間の短縮申請が認められる条件としては、以前に退去強制手続を受けたことがないことや前科がないことなどがあげられます。上陸拒否期間の短縮申請は、2024年6月に始まったばかりの制度です。適用される条件については不明確な部分も多いですので、この制度を利用する場合には、弁護士に相談することをお勧めします。
在留特別許可の義務付訴訟においては、これらの事情が生じたために、入管は現時点において在留特別許可をすべきであることを主張し、在留特別許可の付与の義務付けを目指します。
退去強制令書発付後の在留特別許可の取得は、かなりハードルの高い手続となります。最近は、入管は、退去強制令書発付後の結婚などを理由とする在留特別許可に対しては、かなり厳しい態度をとっています。一方、一旦帰国して正規の在留資格での入国を希望する者に対しては、従前よりも緩やかな基準で許可をしている印象です。どの手続きを選択するかは難しい問題です。弁護士とよく相談した上で、手続を選択することをお勧めします。

よくある質問
|
Q. |
再審情願をしてから結果が出るまでどのくらい時間がかかりますか? |
|---|---|
|
A. |
1、2か月程度で結果が出ることが一般的です。但し、1年やそれ以上の時間がかかる場合もあります。 |
|
Q. |
上陸拒否期間の短縮申請が不許可となった場合、5年間など法定の上陸拒否期間は日本に入国することは絶対にできないのですか? |
|---|---|
|
A. |
上陸拒否期間の短縮申請が認められなかった場合でも、在留資格認定証明書交付申請(いわゆる呼び寄せ手続)を繰り返すことで、2年から3年程度で再来日可能なケースもあります。 |
|
Q. |
義務付け訴訟でビザがもらえたケースはありますか。 |
|---|---|
|
A. |
裁判で勝訴したケースは複数件あります。また、裁判所からの和解勧告で、ビザがもらえたケースもありますが、その正確な数は分かりません。 |
|
Q. |
在留特別許可の義務付けの裁判にはどれくらいの時間がかかりますか? |
|---|---|
|
A. |
個別のケースによりますが、一般的に1年程度の時間を要します。高等裁判所へ控訴した場合には、さらに約6か月かかります。 |
|
Q. |
上陸拒否期間の短縮が認められた場合には、本当に1年でビザがもらえますか? |
|---|---|
|
A. |
上陸拒否期間の短縮許可が得られた場合には、「許可証」がもらえますので、上陸拒否期間が短縮された証明になります。上陸拒否期間の短縮は、従前から「みそぎ帰国」という名前で事実上の取り扱いがなされており、1年後に夫婦関係が壊れていたり、呼び寄せる側の収入が不足しているなどの事情がない限り、きちんと入国ができている印象です。 |
|
Q. |
退去強制令書が発付された後、帰国を拒否したままだとどうなりますか? |
|---|---|
|
A. |
突然収容されて、強制送還させられる場合があります。弁護士に「送還予定時期通知希望申出書」を入管に提出しておいてもらえば、強制送還の約2か月前に通知を受け取ることが可能です。通知を受け取った場合には、余裕をもって帰国の準備をすることが出来ますし、場合によっては、強制送還を停止するための手続をとることも可能な場合があります。 |




